お出かけスポット検索
神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。
条件を指定して絞り込み
-
大日堂は、奈良県の東大寺大仏造営に尽力した行基によって、742年に開かれたと伝えられています。本堂には高さ175cmの「大日如来像」があり、県の重要文化財に指定されています。
-
数多くの文化財を保有する平安時代(829 年)創建の歴史ある寺院です。本堂ではこれまで多くの文化的イベントも行われています。国登録有形文化財の庫裡では会議、レセプション等、また境内では野外イベントも可能です。
-
主な施設(有料)1階 紅葉阪ホール 812席2階 スタジオHIKARI(多目的プラザ)132席3階 練習室
-
全国屈指の大型文化施設として知られる神奈川県立県民ホール本館は、1975年に横浜港を望むこの地に開館しました。以来、ヨーロッパの一流歌劇場の引越し公演から、ポップスコンサート、一般の方の利用に至るまで、幅広いジャンルの催しが行われています。また、県内屈指の規模を誇るギャラリーでは、一般の方の利用と並んで、新進気鋭の作家の個展が数多く開催されているなど、県の芸術文化の創造と振興の中心となる文化施設です。
-
県立座間高等学校の北東側交差点角にある湧水。この湧水は、古くから周辺住民の飲料水として利用されてきましたが、現在でも野菜等の洗い水として利用されています。この湧水の名称については、生活のために必要な水を神様が恵んでくれた、神様が作ってくれた井戸という意味で神井戸(かめいど)と呼ばれています。現在は、昔の約1/10ほどの面積になっているといわれています。
-
天慶4年(941)の創建といわれ、早良親王(桓武天王の同母弟)と、鎌倉権五郎景政を合祀しています。災難除け、学業成就、合格祈願、書道上達のご利益があると言われています。
-
久野にある古墳群は、古墳時代の後期に属する高塚式円墳の古墳としては県下有数のもので、120基程度の存在が推定されています。現在は、1号古墳、2号古墳、4号古墳及び15号古墳などが残っており、このうち4号古墳と15分古墳は発掘調査のあと石室を復元していて、一般の見学ができるようになっています。
-
昭和初期に建てられた古民家を、平成3年に秦野市の蓑毛地区へ移築復元した施設です。令和2年(2020年)4月には、葉たばこ栽培に関わる遺構として、また昭和初期の農家建築を知るうえで重要な建築物と認められ、国登録有形文化財(建造物)に登録されました。家の構造は、当時の一般的なたばこ農家に見られる建築様式で、田の字型四間(よつま)となっており、土間には農具や日用品も展示され、農家の暮らしを知る上で貴重な施設となっています。村民体験や稲刈り、お月見会なども開かれ、自然豊かな周辺をめぐるハイキングも定期的に設けられています。
-
町の天然記念物に指定されているヤマザクラです。源頼朝が植えたという伝承があるとされています。
-
松原神社は、小田原北条氏(戦国時代)以降、歴代城主が崇敬してきた小田原の総鎮守とされています。
-
境内には鎌倉時代の海老名氏一族の国分季頼が国分尼寺に寄進した銅鐘や海老名に伝わる昔話「尼の泣水」に縁のある如意輪観音像が境内に安置されています。銅鐘は国指定の重要文化財となっています。
-
本宮からみて西北の後方に鎮座する。 承久の乱(1221)に際して配流され、ご不運に遭われた三上皇の御霊を慰める為宝治元年(1247)に奉祀された。 御祭神:後鳥羽上皇、土御門上皇、順徳上皇 例祭日:6月7日
-
現存する神奈川県内最大の古墳4世紀中頃から後半に築造された2基の前方後円墳です。平成11年、携帯電話の中継基地工事の際に発見され、発掘調査では、つぼ形や円筒の埴輪が出土しました。第1号墳は墳丘の長さ91.3メートル、山を削って成形した上に、約1.5メートルの盛り土をして築いてあります、後円部は3段、前方部は2段の段築(斜面に段を設ける構造)になっています。1号墳の周辺からは、眼下に田越川流域の逗子市街や相模湾、遠くに富士山や丹沢の山々などを一望できます。反対に、平野部や海上からもこの前方後円墳を望めていた可能性も高く、そのような場所に築くことで、権威や威厳を示していたのではないでしょうか。
-
国指定史跡に指定されている仮粧坂は、鎌倉七口の1つで急峻な道が今も残る切通です。切通とは鎌倉と隣接地域との間の人の移動や物資の流通を盛んにするために、山や丘を切り開いて造られた道のことです。戦では切通を封鎖することで、鎌倉への敵の進入を防いだと考えられています。
-
平安時代後期の武将源義家(八幡太郎)が見つけ詞に詠んだ山桜があり、その後「江戸見桜」と称されています。その他子どもたちがターザンごっこをしたといわれる「ターザンの木」、川崎市の緑地になった「末長熊の森緑地」があります。
-
琴平の地には、1570年頃神明社が祀られていました。その後1826年に香川金刀比羅宮の分霊を勧請神明社と合祀し、旧ご本殿は2007年奥宮を残し、焼失しました。しかし2011年に再建に合わせ花鳥山水画も復元され、時代を伝えています。
-
モース記念碑は、日本近代動物学発祥に尽力したエドワード・S・モースを記念して建てられた記念碑です。
-
麻生不動院の正式名称は「明王山不動院般若坊」(みょうおうざん・ふどういん・はんにゃぼう)といいます。無病息災や家内安全を願うダルマ市が有名です。
-
表門、主屋、各蔵、等の屋敷構えが江戸時代の農村生活の原風景を残している貴重な文化遺産
-
別名、惣左衛門本陣と言われた181坪の建物で、幕末には14代将軍家茂が京に上る際に宿泊しました。明治23年(1890年)、詩人 佐藤惣之助がこの家で生まれ、大正から戦前にかけて活躍しました。
-
天徳寺は、石橋山合戦で活躍した真田与一義忠がいた場所といわれています。その後、戦国時代前半に、相模国守護代上田氏の居城として本格的に築城され、当時は相模国の重要拠点の一つだったとされています。
-
厚木市古民家岸邸は、明治24年に建てられた歴史的な建物で、厚木市指定有形文化財です。母屋は、木造2階建で、寄棟造瓦葺です。この住宅に使用されている木材は、欅や松などで質が極めて高く、仕上げも入念で、どこの部屋を見ても随所に凝った意匠を見ることができます。創建後、2回の増改築が行われており、明治、大正、昭和期それぞれの生活、建築技術、流行などの時代の変化を1軒見学することで感じることのできる大変貴重な建物です。
-
藤沢市に位置する時宗の寺院です。現在の本堂は平成3年に落成したものです。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)
-
高野山真言宗の寺院です。開基は源実朝といわれ、藤沢宿でも最も古い寺院の一つと伝えられています。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)
-
鎌倉の建長寺の末寺として室町時代初期に創設され、観音堂をはじめ清水寺の遺構を受け継いでいます。観音堂、仁王門、仁王像、絵馬は海老名市指定の有形文化財となっています。高台にあり眺めがよく、晴れていれば大山を望むことができます。境内には様々な草木があり、通年楽しむことができます。
-
800年以上の歴史を持つ寺。坐禅と写経は都合の良い日時に予約ができ、初めての体験者も丁寧に指導してくれます。英語での坐禅の解説が可能です。
-
昔は浪切不動とか白滝不動と呼ばれた寺です。境内真下の海の中に、徳富蘇峰揮毫による「不如帰」の碑が立っています。小説「不如帰」の舞台となり主人公の片岡浪江子にあやかり、浪子不動と呼ばれるようになりました。
-
昭和5年に建築されたイギリス人貿易商B.R.ベリック氏の邸宅。現存する戦前の山手外国人住宅の中では最大規模の建物です。設計者はアメリカ人建築家J.H.モーガン。スパニッシュスタイルを基調とした玄関の三連アーチや瓦屋根を持つ煙突など、建築学的にも価値のある建物です。外観はクワットレフォイルと呼ばれる小窓、瓦屋根をもつ煙突など多彩な装飾が施され、内部も白と黒のタイル張りの床や、フレスコ画技法を用いた壁、玄関や階段のアイアンワーク、獅子頭のついた壁泉を備えたサンルームなど見どころがいっぱいです。2Fの婦人の寝室につながるサンポーチからは横浜港を見ることができます。
-
伊勢原市にある神社。上粕屋神社の旧称は「山王社」で、江戸時代の地誌『新編相模国風土記稿』には、上粕屋村の「山王社」と記載があります。
-
松本剛吉は、明治の元勲・山縣有朋と親交の深かった明治・大正期に活躍した政治家(貴族院議員等を歴任)です。建物は、大正12年(1923年)頃に建築されたもので、数寄屋風の主屋と別棟の茶室(雨香亭)・待合等の建物と、築山や水景を伴う庭園から成る、茶道での交流が盛んであった近代小田原の別邸文化を伝える貴重な遺構となっています。
-
石観音堂は、寛文5年(1665年)に明長寺の僧弁融によって開かれた天台宗明長寺の境外の仏堂で、本尊は石造りの如意輪観世音菩薩です。
-
平塚八景のひとつであり、坂東三十三カ所霊場第7番札所でもあります。 金目観音の厨子はとても価値があるもので、国の重要文化財に指定されています。県・市の指定文化財も多く存在します。
-
横須賀市にある「湘南妙義」の別名をもつ山、鷹取山に彫られた巨大な弥勒菩薩尊像です。横須賀市在住の彫刻家、藤島茂氏が昭和35年から約1年かけて製作しました。像高は約8m、像幅約4.5mです。
-
史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館(旧石器ハテナ館)は全国的にも数少ない旧石器時代をテーマにした施設です。史跡田名向原遺跡は、発見された旧石器時代の住居状遺構から、人類の定住化の歴史を語る重要な遺跡として保存されており、平成11年1月に国の史跡指定を受けました。約2万年前の建物の跡がみられるのは、日本でここだけです。また、旧石器ハテナ館では旧石器時代を中心に縄文土器や古墳の副葬品などを展示しており、野外展示では旧石器時代の住居状遺構、縄文時代の竪穴住居、古墳時代の小円墳が復元され、歴史や文化財について学ぶことができます。勾玉・土器・石器作りなどの体験事業を行っています。
-
「NHKみんなのうた」をはじめ、子供たちに向けた愛情あふれる作品で知られる小黒恵子氏の楽曲数やレコードなどが展示されています。
-
ミューザ川崎シンフォニーホールは「音楽のまち・かわさき」のシンボルとして2004年に開館。ステージを取り囲むように配置されたヴィンヤード(ブドウ畑)型の客席が特徴。国内外の音楽家、オーケストラがその音響を絶賛している。
-
丹沢の峠、いより峠にある不動明王は、以前は道標の役割があったと言われています。
-
小田原城の初代城主となった大久保忠世と11代忠真を祀っています。
-
三浦半島を本拠に相模國を治めた三浦氏の最後の武将である三浦義意公をお祀りする神社。永正17年(1520年)創建の古社。小田原城主であった北條氏綱公の意向により居神大明神として祀られたと言われています。

















































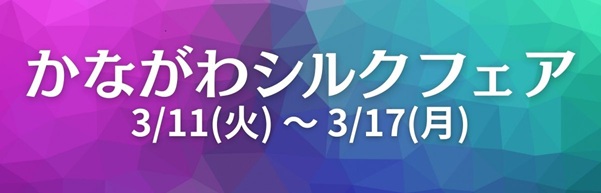
.jpg)



ktbs-bnr240x92.jpg)